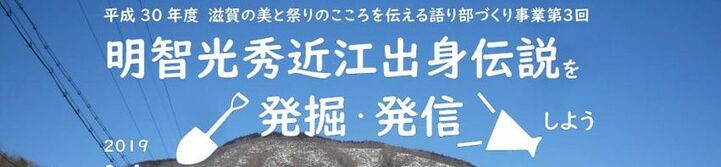時は、戦国のはじまり・・・
今までの明智光秀誕生説と著しく違うのが、光秀公の2~3代前に美濃を出たという事です。
戦国時代のはじまりと言える1467年応仁の乱では、身内同士で東と西に分かれて戦ったり、現代で例えるなら「専務が創業家を乗っ取る」ような下剋上が各地で起こり,徳川家康が天下を取る1600年頃まで続きます。
室町時代の守護大名34家のうち、江戸時代までその地の大名だったのは、たった4家(島津氏・伊達氏・毛利氏と対馬の宗氏)
つまり、残りの30の地域では主君を裏切ったり、見限った人達が大名になっています。それが普通の時代だったと言えます。殆どが謀反人って言ってしまってもいいんじゃないのと、驚きました。
戦国時代のはじまりと言える1467年応仁の乱では、身内同士で東と西に分かれて戦ったり、現代で例えるなら「専務が創業家を乗っ取る」ような下剋上が各地で起こり,徳川家康が天下を取る1600年頃まで続きます。
室町時代の守護大名34家のうち、江戸時代までその地の大名だったのは、たった4家(島津氏・伊達氏・毛利氏と対馬の宗氏)
つまり、残りの30の地域では主君を裏切ったり、見限った人達が大名になっています。それが普通の時代だったと言えます。殆どが謀反人って言ってしまってもいいんじゃないのと、驚きました。
|
元々、佐目を含む多賀は京極氏(多賀高忠)の管轄でしたが、1475年に明智家が頼ったという六角高頼氏(多賀清直)が勝って、1478年に近江守護に返り咲いていますので、佐目は六角氏の管轄になっていたと思われます。
しかしながら、1480年文明美濃の乱では「斎藤利国+土岐成頼+京極氏」に負けています。 佐目は、北からは京極氏、東からは「斎藤氏+土岐氏」が攻めてきた時の 砦の一つとなる場所だったと言えます。 京極騒乱といって、京極家から発生した多賀氏も内輪もめしており、多賀は丁度、京極Vs.六角の取り合いの地でした。 後の関ヶ原の合戦で島津藩が敗走に使った「島津越え」の道は、美濃の時山から、多賀の五僧に入りますが、昔の地図を見ると「時山」は「土岐山」と書いてあり、土岐氏及びその流れを組む明智家も、案外近くの存在だったのかもと驚きました。 |
それまで、南近江を束ねていた六角氏にとって、南近江からつながる鈴鹿山脈の17の峠をすべて抑える事はとても重要な事のように思います。
鈴鹿山脈 北の端が美濃(岐阜)に抜ける五僧の峠と
佐目・大君ケ畑から伊勢(三重)に抜ける 鞍掛峠になります。
鈴鹿山脈 北の端が美濃(岐阜)に抜ける五僧の峠と
佐目・大君ケ畑から伊勢(三重)に抜ける 鞍掛峠になります。
そして、もう一つ。一揆の芽が出はじめた頃です。
佐目に明智十左衛門がやってきた1480年(仮定)頃には、もちろん光秀(十兵衛)も織田信長も生まれていません。本能寺の変が起こる100年程前になります。
室町時代には商業が発達してきて、室町幕府や守護大名以外が力を持ちはじめ、応仁の乱が起こったという側面もあるそうですが、もちろん、商人・農民も力を持ってきていて、既成の支配体制に対して不満が爆発してきました。
そんな中、1466年に歴史上初の一向一揆が現在の守山市金村で起こります。この一向一揆は、支配階級の人が信仰していた天台宗の総本山延暦寺の僧兵に対して、ジワジワと庶民に信徒を増やしていた蓮如の浄土真宗本願寺の門徒が立ち上がった合戦ですが、その後、北陸では本願寺門徒と守護が組んで戦うという事も起こっています。
本願寺第三世覚如の弟子愚咄により豊郷町石畑に創建された 近江七弘誓寺の一つが、1472年に「法蔵寺」と名前を変え、左女(佐目)道場として引越してきます。文献には、応仁の乱で石畑での布教活動が出来なくなって、伊勢や美濃への布教にも便利だという事で佐目になったとあります。地図を見てみると丁度中山道沿いでしたので、確かに応仁の乱にも巻き込まれたでしょうが、僧侶の武装化や一向一揆への備えも もちろん視野に入っていた事は明らかです。その後、左女道場(法蔵寺)は、湖東湖北の一向宗(本願寺)の総本山的な役割を担っていきます。又、佐目の村自体も 甲賀同様 主人が変わったり 主要な地域から離れているので惣村(そうそん)と言われる自治組織が出来ていたと思われます。多賀大社も衆議制で運営されていた時期です。
そんな場所を 六角高頼が明智家を配置するのに選んだとしてもおかしくありません。いや、すばらしいセレクトなのではと思われます。一向宗を仲間にする為に、新たに息のかかった明智家を配置する。その伏線は、六角氏家臣であった小川氏により、京極騒乱が始まった1470年に 佐目から美濃へ勧請された十二相神社が再建された事からも、根回しができていたのではと推測されます。残念ながら、佐目の古文書類は、殆ど まだ調べられずにいますので、今後 法蔵寺も含めて 何か発見される事を期待しています。
因みに、その時 六角氏の家臣だった小川氏の子孫は、後に佐和山城主になり、明智光秀 山崎の合戦に昔の旧き好みにて同心して没落したという小川土佐守です。
次回も もう少し 左女道場や 佐目にある山城についてお話ししたいと思います。
室町時代には商業が発達してきて、室町幕府や守護大名以外が力を持ちはじめ、応仁の乱が起こったという側面もあるそうですが、もちろん、商人・農民も力を持ってきていて、既成の支配体制に対して不満が爆発してきました。
そんな中、1466年に歴史上初の一向一揆が現在の守山市金村で起こります。この一向一揆は、支配階級の人が信仰していた天台宗の総本山延暦寺の僧兵に対して、ジワジワと庶民に信徒を増やしていた蓮如の浄土真宗本願寺の門徒が立ち上がった合戦ですが、その後、北陸では本願寺門徒と守護が組んで戦うという事も起こっています。
本願寺第三世覚如の弟子愚咄により豊郷町石畑に創建された 近江七弘誓寺の一つが、1472年に「法蔵寺」と名前を変え、左女(佐目)道場として引越してきます。文献には、応仁の乱で石畑での布教活動が出来なくなって、伊勢や美濃への布教にも便利だという事で佐目になったとあります。地図を見てみると丁度中山道沿いでしたので、確かに応仁の乱にも巻き込まれたでしょうが、僧侶の武装化や一向一揆への備えも もちろん視野に入っていた事は明らかです。その後、左女道場(法蔵寺)は、湖東湖北の一向宗(本願寺)の総本山的な役割を担っていきます。又、佐目の村自体も 甲賀同様 主人が変わったり 主要な地域から離れているので惣村(そうそん)と言われる自治組織が出来ていたと思われます。多賀大社も衆議制で運営されていた時期です。
そんな場所を 六角高頼が明智家を配置するのに選んだとしてもおかしくありません。いや、すばらしいセレクトなのではと思われます。一向宗を仲間にする為に、新たに息のかかった明智家を配置する。その伏線は、六角氏家臣であった小川氏により、京極騒乱が始まった1470年に 佐目から美濃へ勧請された十二相神社が再建された事からも、根回しができていたのではと推測されます。残念ながら、佐目の古文書類は、殆ど まだ調べられずにいますので、今後 法蔵寺も含めて 何か発見される事を期待しています。
因みに、その時 六角氏の家臣だった小川氏の子孫は、後に佐和山城主になり、明智光秀 山崎の合戦に昔の旧き好みにて同心して没落したという小川土佐守です。
次回も もう少し 左女道場や 佐目にある山城についてお話ししたいと思います。
vol.6 につづく
COPYRIGHT ©3gin Site powered by Weebly. Managed by Z.com Studio